直前期に「何をやればいいか分からない」「新たな問題に手を出すべきか」と迷う受験生は多いはず。
加えて、試験当日も「緊張で集中できない」、「マークミスが怖い」、「持ち物の準備が不安」など、不安がいっぱいだと思いますし、私もそうでした。
この記事では、中小企業診断士1次試験の直前期・試験日の行動に絞り、合格点60%達成を狙う具体的な戦略を、筆者自身の実体験とともにまとめました。
↓1次試験の勉強方法はこちら
まとめ
直前期の勉強は新しいこと、全然理解できてないことには手を出さない。
過去問や問題集を中心に既に何回か取り組んだことのある問題で、間違えた箇所や、理解や記憶が少し怪しい箇所に絞って幅広く数多く取り組み、確実に取れる問題を増やし、全科目の平均で6割をとる。
試験中は、各科目の難易度が毎年変わることを念頭に置き、出来の感触で一喜一憂せず目の前の科目に集中する。
各科目の難しい問題や計算に時間がかかりそうな問題は飛ばして、必ず全問取り組む。
いきなり回答用紙にマークせず、ある程度問題を解いてから(10問くらい)まとめてつける。最後には必ずマークシートのチェックの時間を入れる。
各問題について選択肢を絞れてる、全く分からないを、〇、△、×とつけておき、〇は最終確認、△は残った選択肢の要精査、×は割り切って確率での正解を目指す。
表などで覚えてるものは空白に表を書いてしまう。
試験前の休み時間は意外と長いので記憶系の問題を優先して最終の詰め込みをする。
試験直前の勉強方法
1次試験は幅広く出題されるので新しくできる問題を1問増やすことより、基本問題で少し理解が怪しい問題を確実にできるのを増やすのが大事です。
新しい問題は1から理解するところから始まるので1問を取り組むのにとても時間がかかります。
自分の感覚では新しい問題はだいたい3回くらい解いて正解できるくらいなので、その時は理解できても試験で出てきた時に外す可能性が高くなるため、直前期にはやらない方がいいです。
既に取り組んだことがある過去問や問題集を使って、いつも正解する問題ではなく、間違えたところや少し理解や記憶が怪しいところの復習をメインで取り組んだ方がいいです。
(問題のできを、できた、あと少し、出来なかったで〇、△、×、とつけておくと後で復習しやすい)
問題を厳選することで残りの短い時間で周回できる早さを上げて、確実にできる問題を増やしていくことで点数アップが期待できます。
7科目全体を周回して復習することで、総合点で合格点をとれる可能性があがります。
各科目の難易度は毎年変動するので手広くやっておくことが大事です。
答え合わせの際は◯✕だけでなく、どこが違うのか、どこまで合っているのかを整理することで1問から得られる情報が増えて復習の質があがり点数アップになります。
試験当日
持ち物
・受験票の写真(最悪スマホでとってコンビニに行く)
・受験票
・筆記用具(鉛筆、消しゴムの予備含む。鉛筆削り、シャーシンも。)
・時計(スマートウォッチはダメ)
・上着
・昼食
・参考書や問題集(直前に詰め込める程度)
全体
基本的には2日あるので、途中で集中がきれるなら、科目間の休憩時間の最後の詰め込みはやりすぎずに必要に応じて休憩しましょう。
(私は試験中はずっと集中できるので最後の最後までパソコンを開いてスタディングで復習してました。)
試験日はなるべく早く寝て早く起きて体調を整えて、朝一から終日まで集中が切れないようにしましょう。
7科目もあるので、途中で受けた科目の出来がどうだったとか考えるのはやめた方がいいです。
得意不得意は気にせず、簡単な科目もあれば難しい科目もあることを念頭に置くのがいいです。
難しい科目で4割を切らず、全体で6割を取ることを意識しましょう。
朝一から試験後までスマホや音が鳴る機器は切っておくと、試験を安心して受けることができます。
試験前
開始の3時間前には起きて、2時間前には朝ご飯を食べることで脳がエネルギーを使える状態で、朝一の科目から望めるようにしましょう。
会場に入室可能な1時間前にはついた方がいいです。(公共交通機関の遅れもあるのでもっと早くてもよい)まずは、席を見つけて、受験票や筆記用具をセットし、トイレの場所の確認が必要です。
休み時間
記憶系の問題の最後の追い込みをギリギリまでかける。トイレに行くのは次の科目の回答用紙の配り出しあたりで行けば混まないし時間が有効に使えます。
解答用紙を配るくらいまでならトイレや直前の追い込みをすることができます。
私の場合はレッドブルを休み時間にちょくちょく飲んでたから、各科目で集中ができた気がします。
試験中
1問にこだわらず、よっぽどあってそうなのは〇、分からないところは×、ある程度あってそうだったり絞れているものは△など印をつながら問題をどんどんと進め、必ず全問取り組めるペースでやる。
×の中でも確率的には4分の1や5分の1はあってるはずなのである程度割り切って問題を解く。
(×とつけた中でも意外とあっていることもある)
私の財務会計の場合は、1問目や初めの方に時間があっても解けなかった計算問題が多かったです。しかし、後半は解きやすい計算の問題や記号問題が続いてたので先にやって、全体をまず解きました。
飛ばした問題のマークミスをするのを避けるため、マークシートはある程度問題が進んでから一気につけていき、まずは〇のものだけをつけていきます。
問題を解く時間、マークする時間に分けて集中することでマークミスが防ぎやすいです。
最後には必ずマークチェックの時間をつくります。
選択肢の中で間違いを見つけた箇所には線を引いておき、その選択肢には斜線を引いて、もう読まないようにして選択肢を絞るのがよいです。斜線が増えた分だけ点数が取れる確率がアップします。
経営法務などの記憶系の問題で表などで覚えてるものは空白に表を書いてしまって確実に点数につなげる。
確率的に何もしなくても20点~25点はあります。基本問題が何問か解けることでプラス30点くらい。選択肢を絞って点数を取れる確率を上げて60点以上を目指せると考えています。
経済学、経済政策
グラフの問題が多く出ますが、線を書き込んで動き方が合ってるか確認する。
財務会計
計算問題は時間が取られます。方針分からない状態で、考え込むと時間が足りなくなるため飛ばしてあとでやった方がよいです。
暗記系の問題で解きやすい問題もあるので必ず全問取り組むようにする。
財務指標は定義式を書いてみて確認したり、変形して考えられないか試してみる。
企業経営理論
文章が多い問題が多いですが、普通に考えてどこかにおかしいところが見つかることもあるので、選択肢の間違いを探していけます。選択肢を絞ることで正解の確率を上げることができます。
運営管理
問題数が多いです。計算問題もあるの方針がわからない場合は後回しで、まずは全問やりきる。
正誤問題はわかるところから選択肢を絞って正解の確率を上げる。
経営法務
表にして覚えている用語などもあると思いますので空欄にメモとして書いた方がいいです
似てる選択肢はどこが違うのかマークしておきそこだけに着目し時間を短縮したり、分かるところだけでも選択肢を絞って正解の確率をあげる。
経営情報システム
知っている情報からなるべく選択肢を消して正解の確率を上げる。
違う言葉の説明をしてないかや、英字の意味を考えて答えがあってそうなのか想像をしてみるのも有効です。
中小企業経営、政策
各業種の大まかな動向を覚えておきたいです。最後の科目になりますので、直前の直前まで覚えるのを頑張った方がいいです。
表にして覚えている用語もあると思いますので空欄にメモとして書いた方がいいです。
以上、1次試験の直前や、当日の得点アップにつながる過ごし方でした。これから1次試験を受験される方にも、何かを取り入れてもらって合格を勝ち取ってもらえればと思います。
さいごに
試験本番は、これまでの知識だけでなく「どう動くか」も得点を大きく左右します。
焦りそうな場面で落ち着いて対処できるように、あなた自身の行動ルールをこの記事を通じて整理できたなら、それだけで合格に一歩近づいています。
直前期は新しい問題に手を出すより、確実に取れる問題を増やす戦略が最も効率的です。
試験当日は、〇/△/×の印をつけることで迷う時間を減らし、“全問に触れる”ペースで取り組み正解の確率を上げて得点チャンスを最大限に広げましょう。
これから1次試験を受験される方は全科目平均で60点以上獲得し合格を勝ち取って下さい。

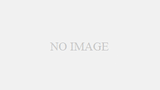
コメント