1次試験受験後に採点して合格が分かってから、そのまま2次試験も合格しようと思うとあまり休む間もなく2次試験の準備に入らないといけないです。
事例Ⅳの2次試験は1次試験とは異なり幅広い分野が出題されるわけではなく、ある程度決まった分野からの出題となります。
事例Ⅳでは過去問を使った場合は80分まとまった時間が必要となりますが、なかなかその時間を確保するのが難しい方が多いと思います。
しかし、事例Ⅳは必ず本番通りの時間を取れなくても、スキマ時間を使って解き方のコツをつかめば点数アップが期待できます。
また、なるべくまとまった時間は事例Ⅰ~の練習に使って総合的な点数をあげて、合格の確率を上げるのが2次試験合格に向けては効率が良いと思います。
私の場合も事例Ⅳは、毎日のスキマ時間を勉強のメインとして、他の事例にまとまった勉強時間をあてることで総合点で240点以上を取ることができました。
↓事例Ⅳの再現答案
このページでは私がやったスキマ時間での勉強方法を紹介したいと思います。
まとめ
事例Ⅳはスキマ時間でも得点アップできる。
過去問の代わりに事例Ⅳの全知全ノウを使って、毎日のスキマ時間で、時間を計りながらやって効果的に対策。
試験直前に時間間隔の調整と全知全ノウの解法の理解度チェックとして過去問をやる。
直近の過去問は全知全ノウがないので、別で解いてふぞろいで採点をする。
過去問を解く際は途中計算の狭さを知っておくため、予備校から本番用の解答枠を入手してやるとよい。
過去問は1つの事例のやる時間を確保できる場合は通しでやればよいが、設問ごとに区切って、時間を測って全部で60分くらいを目安にやってもよい。
事例Ⅳの形式
大枠では以下のような設問が4つ程度あります。
設問1 経営分析
確実に点数が取れる問題です。与件に沿って特徴がある指標を回答する。与件の言葉を使って収益性、効率性、安全性の指摘をする。他に時間をかけたいのであまり時間をかけずに指標の計算と記述をする。
設問2、3 損益分岐点分析、投資意思決定会計などの計算
計算問題がメインになってきます。計算方法を習得するまでに時間がかかります。損益分岐点分析では変動費と固定費を正確に求める、セールスミックスの問題が解けることなどが必要です。投資意思決定では投資がいつなのか、利益はどの段階なのか、運転資本の増減はあるのかなど見極めて正確に正味現在価値などを求めることが必要です。
設問4 今後の助言や問題点などの記述
1次試験の知識を使って今後の事業をする際の注意点や、現状の財務上の問題点などを記述します。
近年は特に近年は特に合格者との差が開きやすい傾向にあるようなので、合格点の60点は欲しいです。
使ったテキスト
そんなに使ったテキストは多くないです。
私の場合は2年かかりました。効率的に勉強して合格するなら、全知全ノウだけでいいです。
事例Ⅳ全知全ノウ(2年目に使用)
過去問がテーマ別に掲載されているため、分野が絞られていて縦割りで取り組めるため効率的に点数アップが望めます。
オリジナル問題ではなく過去問が載ってるので、過去問を取り組むのと同じ効果が得られます。
重要度が示されてるので試験までの時間に余裕がない場合はAの問題だけをするなど調整ができます。
このテキストは過去問の代わりとして使える上、スキマ時間にもできるので効率的に合格するには外せないです。
注意点は、最新年度がないことと時間が本番の80分での練習ができないことです。最新年度は時間を設問ごとに区切ってでもいいので時間を計り、採点はふぞろいで途中式まで確認しながらやるとよいです。
また、本番の計算スペースはかなり狭いので、予備校のサイトなどでダウンロードして練習しておくことがおすすめです。
(私は1、2年目どちらもやっておらず、本番で枠がはみ出すくらいまでいっぱい書いて読みにくくなってしまいました)
30日完成(1年目に使用)
私みたいに1次試験の財務会計が合格点を達しないレベルであれば、このテキストをやることで、2次試験の事例Ⅳが取り組みやすくなります。
解きやすいオリジナル問題が収録されていて、基本的なところから学べます。
タイトル通り合格点を目指すもので、私はこれだけを使って1年目に56点と合格点に近しい結果でした。
ただし、過去問とは別でやることになるので過去問の時間を別で取る必要があるため、時間に余裕がある場合のみやることをおすすめしたいです。
1年目の私は、評判が良かったこのテキストを先に手に付けました。
しかし、他の事例の勉強が足りず、合計で204点と合格点には程遠い点数となりました。
短期間で効率よく合格しようと思うと全知全ノウをやった方が、過去問ができるため効率的に点数アップできます。
基礎からしっかり理解を深めて勉強したいという場合にはおすすめです。
損益分岐点分析、正味現在価値などの基本問題をといて計算方法を習得できます。
ちなみに簿記の観点も勉強できるので、簿記も目指す方はやっておいて損はないです。
テキストの使い方と効果
事例Ⅳ全知全ノウ
以下のテーマ別に分かれた構成になっています。必ず時間を計ってやるようにします。私は、基本毎日(日曜日以外)のスキマ時間で6周程度周回をしました。
■経営分析
ノウハウに従って、売上高に対する比率を算出、与件の言葉を拾って収益性、効率性、安全性にコメントをする、の流れを問題を周回して素早くできるようになりました。
特徴か、問題か、課題か、何が問われてるか意識して回答できるようになりました。
縦割りで解くことで計算方法や、点数アップにつながる設問の与件の言葉の拾い方、設問への回答のやり方が効率よく習得できました。
■損益分岐点分析
損益分岐点売上高や目標売上高などの公式を覚えつつも、利益=売上ー変動費ー固定費、の基本式を意識し、問題を周回しながら理解を深めるようにします。解説が丁寧に書かれているので理解をしながら、縦割りで周回することで効率よく解き方が学べました。
模範解答を見ながら途中式として何を書くことで点数になるのかを確認でき、部分点の取り方が分かるので点数アップに繋げることができました。
解説が丁寧であり、変動費と固定費の分け方を正しく理解でき、費用構造の違いによる財務面への影響を理解しながら勉強できるので、正しい計算方法や記述問題に対する指摘ポイントが学べました。
損益分岐点分析の記述問題の解答例を覚えおいたので、試験本番でも使えるところがあり点数アップになりました。
■投資意思決定
投資する額やいつの時点の投資なのか、各年度の利益はいくらか、をして表にして投資額やキャッシュフローの整理をするまでの手順を、問題集を周回して習得することで、試験本番でも同じように解くことができ点数アップになりました。
■セグメント別会計
損益分岐点分析と同じように変動費と固定費を分け、限界利益や貢献利益を出して事業別の業績の評価の仕方が習得できました。
限界利益や貢献利益から、どの事業に注力するのかや廃止するのかを問題を通して判断できるようにし、記述も慣れておくことで本番でも使い点数アップにつながりました。
■キャッシュフロー計算
近年はあまり出題はないです。しかし出てきたときに備えて練習が必要です。営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローなの算出の流れを問題を周回して覚えました。
正負どっちなのかや、特別利益・損失など各項目が営業キャッシュなのか財務キャッシュフローにするのかを問題を通して決めておきました。
記述問題の書き方を理解し、覚えておくことで、設問4の助言や問題点の指摘で使えるようにしておくことで得点アップが狙えました。
■その他計算問題
損益分岐点分析の計算のように変動費と固定費を分けて、利益の基本式をつかった計算を練習する。限界利益や貢献利益をみながらどの事業を注力や廃止するのかや、費用構造がどう違うのかの確認をしたり、それら使って問題点や助言をする練習をして計算力や記述力をつけることができました。
為替差損益の計算練習やオプション取引、為替予約など記述問題にも備えておきます。
30日完成
このテキストは2次対策に十分に時間があって基礎から長期的に取り組めみたい方であればやることをおすすめします。
私は2年やって6周程度の周回をしました。
■財務分析
オリジナル問題を使って、収益性、効率性、安全性でたくさんの指標を上げて式の構造から確認ができました。指標に対する説明も与件からたくさん引用でき、回答のコツが練習ができる。
ただし、短く書く練習もしないといけないので過去問でも練習が必要です。
簿記の観点の問題もあり、財務諸表の計算方法や構成が学べました。
■損益分岐点分析/セグメント別損益計算
簡単な問題で基本式を使って計算練習ができました。ひねった問題がなく、解き方の方針が分かりやすいので、テーマに集中して取り組めました。
1年目に本番で固定費、変動費が明示されてない場合が、ドンピシャで出て来たので思い出して解けました。
■プロダクトミックス
1個当たりの限界利益を基に優先順位を決めたり、貢献利益も加味して生産の優先順位つける、線形計画法で生産量を決める、などして最大利益を計算するという方法を学べました。
このテキストでも、1個当たりの限界利益が高い順で生産の優先順位を決めるというのを勉強していたので、合格した年度の本番でも思い出してなんとか計算することができました。
■キャッシュフロー計算
営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローの一通りの項目や、正負の確認が簡単な問題を通してできました。
■投資の経済性分析
簡単なオリジナル問題を使って基本的なところから学べました。大まかな流れの確認をすることができました。運転資本が増減する場合のキャッシュフロー計算方法は、このテキストが印象に残っていて、合格した年の本番でも対応できたし、記述に入れて部分点をゲットできました。
以上、私の場合のスキマ時間を活用した事例Ⅳの勉強方法でした。
これから2次試験に向けて勉強をされる方は、なるべくスキマ時間を事例Ⅳにあてながら、まとまった時間を他の事例に当てることで効率よく点数アップする勉強をし、総合点で合格を勝ち取って下さい。

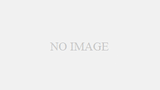
コメント