はじめに
中小企業診断士2次試験の中でも、多くの受験生が苦戦するのが「事例Ⅳ(財務・会計)」になるかと思います。
計算問題を中心に記述問題とともに構成され、80分という限られた時間の中で正確かつスピーディに回答することが求められます。
合否を分ける大きなポイントは「時間配分」と「本番での柔軟な対応力」です。
理想のペースを意識しつつも、想定外の事態にどう対応するかを事前に考えておくことが、合格への大事なポイントです。
まとめ
事例Ⅳの理想の時間配分は「設問1:15分」「設問4:10分」「設問2:25分」、
「設問3:25分」、「見直し:5分」
ただし、初見問題の中では理想通りにはほぼならないので本番は柔軟性が大事。記述問題に思った以上に時間を取られたり、NPVやCVPを完答できないケースがほとんど。
対応策として「NPVやCVPは1問だけを解く」など、事前に取り組むべき優先順位を決めておくことが重要。
80分の中で得点を最大化する戦略をとるために、完答を目指す意識は持ちつつも「とれる部分点を確実に拾う戦略」が大事。
時間の使い方と本番の臨み方
① 事例Ⅳの80分をどう使うか
事例Ⅳは、財務・会計の知識をベースにした計算問題が中心です。与えられた80分をどう使うかで得点が大きく変わります。理想的な時間配分は以下の通りです。
私が考えていた理想的な時間配分と解く順序を次のように考えてました。
| 設問 | 時間 | 狙い |
|---|---|---|
| 第1問 | 15分 | 取り組みやすく型に沿った問題が多いため、確実に素早く得点を積み上げる。 |
| 第4問 | 10分 | 財務指標への影響、経営改善策・問題点の記述問題が多く、型に沿って素早く点数を稼ぐ。 |
| 第2問 (CVP前提) | 25分 | NPVと比較して解きやすいので先に解いて点数を稼ぐ。理想は完答だが、最低1問は解く。 |
| 第3問 (NPV前提) | 25分 | 残った時間でじっくり時間をかけて解く。理想は完答だが、最低1問は解く。 |
| 見直し | 5分 | 解いてない問題がないかチェックや、部分点が稼げる記述や途中計算になってるかチェック。 |
確実に回答をすることができる第1問や第4問を、過去問で取り組んでいたペースで分配し、残り時間を第2問や第3問に当てた配分となっています。
② 本番で起こり得るイレギュラー
過去問を繰り返しやっていると、解ける状態の問題を解くことに慣れてしまい思わず完答を目指したくなってしまうと思います。
しかし、初見問題の試験本番では理想通りに進まないことがほとんどですし、私は2年受験して2回とも理想どおりにはなりませんでした。
例:
第1問や第4問の記述問題で、思った以上に時間を取られてしまったり、そもそも何を書けばよいか思いつかない。
CVPやNPVの計算が複雑で、最後まで完答できない。
計算過程に迷ったり、難しい問題を考えすぎることで時間が足りなくなる。
こうした「想定外の事態」に直面すると、焦りからミスを誘発し、全体の得点を落とすリスクがあります。
実際には、第2問や第3問の初見の問題を限られた時間で完答はほぼできないので、本番中に問題に応じて解く順序や時間配分を柔軟に対応し、完答をするのか一部だけを解くのかを考えて対応することが大事です。
③ 柔軟な対応力を持つことの重要性
本番で大切なのは「柔軟な対応力」です。理想のペースを意識しつつも、状況に応じて戦略を切り替える準備をしておきましょう。
NPVやCVPは1問だけ解く完答が難しいと判断したら、部分点を狙って1問だけを確実に仕上げる。
記述問題は深追いしすぎず、思いつく限りのキーワードを押さえた回答を優先する。
見切りの判断を早めに「あと数分で解けるか?、決めた時間内に解けるか?」を常に意識し、難問に固執しない。
このように、事前に「もし時間が足りなかったらどうするか」を事前にシミュレーションしておくことが、合格点を取る確率を高める重要な戦略となります。
④ 完答を目指す意識と部分点戦略
もちろん、理想は全問を完答です。しかし、現実的には「部分点を積み上げて合格点を超える」ことが最も重要です。
経営分析は必ず得点源にする。
記述問題は最低限のキーワードを盛り込んでなるべく点数を確保できるようにする。
計算問題は途中式を丁寧に書き、部分点を狙う
CVP、NPVは1問解ければヨシとする
このように、イレギュラーを想定しておきながら、完答できればラッキー程度に思って、部分点を確実に拾う戦略が、合格への最短ルートです。
私が合格した年の、実際の時間配分は以下のとおりでした。
| 設問 | 時間 ()は理想からの乖離 | 結果 |
|---|---|---|
| 第1問 | 20分 (5分オーバー) | 初見で記述の書きづらさがあったので時間はかかったが、型にはめ込んで与件文をエイヤーで入れて少し時間オーバー。 |
| 第4問 | 20分 (10分オーバー) | 一読しただけでは何を答えればよいか分からず。過去に問われていた観点を思い出せる限りで何とかピックアップ。要素が少なすぎたのですぐに本回答はできず考え込んだ。第2問や3を先に読んだが、頭に入らなかったため、結局そのまま思いついた要素に冗長的な文章で文字数を埋めて本回答。 |
| 第2問 (CPV) | 25分 (時間通りだが、 1/2問しか回答できず) | 時間当たりの限界利益の着目はすぐに分かったが、解けそうだが解けない状態を何度もやり直して時間をロス。結局、時間がオーバーペースでなんとか2問中の1問だけを回答、2問目を回避して、第3問へ移行。 |
| 第3問 (NPV) | 12分 (十分な時間使えず。 2/3問しか回答できず) | 残り時間の想定の半分程度の時間で回答。思ったよりも解きやすかったため、3問中の2問のNPVを何とか回答。 |
| 見直し | 3分 | 計算方法を理解していることを採点者に示すために計算過程の文章を少し追加。 |
第2問や第3問で時間内で解ききれなさそうな問題は回避し、解けそうな問題で部分点を確実に得点を積み重ねていったことで、取れるころで点数を落とさないリスクを下げ、合格点を取ることができました。
以下は実際の再現回答です。
↓令和6年再現回答
さいごに
事例Ⅳは「時間との戦い」であるため、問題を見渡してどこを確実に解くのかを見極めることが大事です。
理想の時間配分を頭に入れつつ、本番では柔軟に対応できる準備をしておくことが、合格と不合格を分ける最大のポイントです。
80分という限られた時間を完答を目指す強い意志を持ちながらも、部分点を確実に積み上げてなるべく高い得点がとれる戦略で臨みましょう。
2次試験の最後まであきらめず頑張ってください。

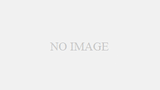
コメント