まずは、受験本当にお疲れさまでした。
長い学習期間を経て、ようやく2次筆記試験を終えた今、心身ともに大きな解放感を味わっている方も多いと思います。
ここまで積み重ねてきた努力は、結果がどうであれ、必ずご自身の力になっています。
さて、試験が終わった直後にぜひ取り組んでいただきたいのが「再現答案の作成」です。試験が終わったばかりの今だからこそ、記憶が鮮明で、当日の思考プロセスを正確に残すことができます。再現答案は単なる記録ではなく、次の成長のための土台となります。
再現答案を残すことによるメリットは多くありますので是非とも取り組んでください。
とってもつらい作業にはなりますが、、、
私もこれをしたからこそ2年目の受験で飛躍的に点数を伸ばすことができました。
まとめ
- 再現答案を作ることで「初見問題に対する今の実力」を客観的に把握できる
- 答案を分析することで「次に向けた大きなレベルアップ」が可能になる
- 採点基準が非公開だからこそ、再現答案は「採点基準を知る貴重な材料」になる
- 口述試験に向けて知識や思考を整理できる
- 「あの要素を書ければよかった」という気づきが診断士としての実力を底上げする
今の実力を客観的に把握できる
2次試験は初見問題に対して、限られた時間で論理的に解答を組み立てる力が問われ、そこが試験の難しさになってます。
再現答案を作ることで、当日どのように与件文を読み、どのように解答を組み立てたのかを振り返ることができ、次へのステップに重要な役割を果たします。
「設問要求を正しく捉えられていたか」「与件文の根拠を答案に反映できていたか」などを確認することで、自分の強みと弱みが明確になります。
これは、合否に関わらず今後の成長に直結する大切な作業です。
分析することで次に向けて大きくレベルアップできる
再現答案を作った後は、予備校の模範解答や解説動画などと照らし合わせて分析しましょう。
- 「なぜこの表現を選んだのか」
- 「他の切り口はなかったか」
- 「時間配分は適切だったか」
こうした振り返りを通じて、答案作成のプロセスを改善できます。特に、設問解釈や与件文の根拠抽出における癖を把握できれば、もし次回がある場合に答案精度は飛躍的に向上します。
私もこれをしたからこそ、2年目に大きく実力を伸ばすことができました
採点基準が非公開だからこそ価値がある
中小企業診断士2次試験の採点基準は公表されていません。そのため、受験生にとって「自分の答案がどう評価されるのか」はブラックボックスです。
しかし、再現答案を残しておけば、後日合格者の答案や予備校の採点傾向と比較することができます。
これにより「どの要素が評価されやすいのか」を推測でき、次に挑む人にとっても大きな価値を持ちます。
口述試験に向けて整理ができる
筆記試験を突破すると、次は口述試験が待っています。口述試験では、与件企業の課題や施策について口頭で説明する力が求められます。
再現答案を作っておくと、自分がどのように考え、どのような助言をしたのかを整理できるため、口述試験の準備がスムーズになります。特に「自分の答案を言葉で説明できるか」を意識しておくと、本番での受け答えに自信が持てます
合格率がほぼほぼ100%とはいえ、何もしゃべれなくて不合格という最悪の事態を回避できます。
新たな発見が診断士としての実力を高める
再現答案を振り返ると、「あの要素を書ければよかった」「この切り口もあった」といった気づきが必ず出てきます。
これらは単なる反省ではなく、診断士としての思考力を磨く貴重な発見です。
診断士は実務においても、限られた情報から課題を抽出し、助言を行う役割を担います。再現答案を通じて得られる気づきは、試験対策を超えて、実務としての基礎力を養うことにも繋がります。
さいごに
試験を終えた今は、まずは自分を労うことと、周りへの感謝をしてください。
その上で、ぜひ再現答案を作り、振り返りを行ってみてください。
再現答案は「自分も含めた次に挑戦する人たち向け」だけではなく、「自身の診断士としての成長につながるもの」です。
今の自分の実力を客観的に見つめ、次のステージに向けて一歩踏み出すための大切なツールになります。
診断士試験はゴールではなく、スタートラインです。再現答案を通じて得られる学びを糧に、これからの成長に活かしていきましょう。
以下、私の再現回答です。
↓令和5年再現回答
↓令和6年再現回答

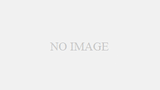
コメント