中小企業診断士の2次試験、事例Ⅳは唯一の「数字で勝負する」試験です。
その中でも設問1の財務分析は、試験のはじめに登場する“準備運動”のような位置づけですが、実はここでの時間配分が事例Ⅳ全体の得点アップに重要です。
設問1は、財務諸表から企業の課題や特徴をを読み取り、定量・定性的に指摘する問題です。
解きやすい問題ですが、時間をかけすぎると中盤にある計算問題(CVP・NPVなど)に手が回らなくなるのがこの設問1の怖さです。
この記事では、設問1を「15分で解き切る」ためのポイントと、財務分析の視点・指標の選び方・特徴などの記述方法まで、実践的に解説します。
まとめ
設問1は「15分以内」で解くのが大事。時間をかけすぎると後半の得点チャンスを逃す。
財務分析は「収益性・効率性・安全性」の3視点から、使える指標を選び、定量的・定性的に回答する。
近年のトレンドとして生産性の指標も覚えておく。
本番は指標の選定や記述の仕方で迷うと思いますが、ある程度で割り切って時間を守って回答をすることが大事です。
過去問の周回で“型”を身につけて10分で解く練習をすれば、15分攻略は十分可能です。
設問1の位置づけと時間配分
事例Ⅳは設問が4つからなる80分の試験です。
設問1は最初に取り組むべき問題で確実に点数が取れる問題です。財務諸表(BS/PL)を基にして、与件文と照らし合わせて、企業の課題を定量的・定性的に分析する問題です。
ここで時間を使いすぎると、残りのCVP分析、NPV/投資意思決定、その他助言問題を取り組む時間がなくなります。
そのため、設問1は「15分以内」で解き切ることが合格戦略の第一歩です。
財務分析の代表指標と特徴
設問1では、以下の3つの視点から指標を選び、企業の課題を分析します。
| 種類 | 代表指標 | 見極め方 |
|---|---|---|
| 収益性 | 売上高総利益率、営業利益率、売上高経常利益率 | 売上高総利益、販管費、利息の大きさを見てどれを使うか判断をする。 |
| 効率性 | 有形固定資産回転率、棚卸資産回転率 | 資産が有効活用できてるか、在庫の滞留状況で判断する。 |
| 安全性 | 負債比率、自己資本比率 | 借入金や自己資本をみて判断する。借入金が大きい場合が多い。 |
※試験では、与えられた財務諸表から「前年と当年」、「他社と自社」などの違いを読み取り、特徴を抽出するのが基本
良い指標が1つ、悪い指標が2つなど設問の指示に正しく従う。(間違いを防ぐため〇、×、×なとメモする)
小数点何桁(2桁が多い)で回答するのかが注意点。(間違いを防ぐため、〇、〇〇などメモする)
特徴などの記述は、〜(与件文)で収益性がよく、〜(与件文)で効率性がよく、〜(与件文)で安全性がよい、など与件分から定性的に答えるのがテンプレです。
本番は指標の選定や記述の仕方で迷うと思いますが、ある程度で割り切って時間を守って回答をすることが大事です。
特徴、課題、問題点の違いを認識し適切に回答することが大事です。
令和4年の試験でも出ている、近年のトレンドである生産性の指標(労働生産性、付加価値率、労働装備率など)の回答もあり得るので押さえておく。
収益性では売上高総利益率かそれ以降か、安全性は長期と短期の、などで切り分けができることも頭に入れておく。
15分で解くための実践ステップ
与件分を確認し、定性的に指標の当たり付け【5分】
財務諸表から売上高の比率を基準に定量的に指標を当たりづけ(BS・PLの項目の基準に注目)、
与件文と照らし合わせて指標を3つ選定(収益性・安全性・効率性から)【5分】
特徴の記述(テンプレに沿って)【5分】
この流れを過去問で何度も練習すれば、本番でも15分以内で安定して解けるようになります。
過去問では周回し10分を目安に取り組めば本番の初見問題でもでも15分程度で解けるようになります。
おすすめはやっぱり事例Ⅳの全知全ノウハウです。
↓全知全ノウを活用したスキマ時間での事例Ⅳ勉強法
所見問題は指標や記述内容に迷い時間ロスがありますのでそれも想定しておくように練習しましょう。
さいごに
事例Ⅳの設問1は、パターン化された問題です。
だからこそ、「型」を身につければ、誰でも得点源にできます。
重要なのは時間をかけずに、確実に得点することです。
そのためには、過去問で「指標の選び方」「記述の方法」を徹底的に練習しましょう。
設問1を15分で突破できれば、後半の難問に余裕を持って挑めます。
それが、事例Ⅳで合格点を取るための最短ルートです。
事例Ⅳを攻略して2次試験を突破に向けて頑張ってください。

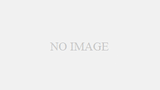
コメント