中小企業診断士2次試験は、80分という限られた時間の中で、設問を分析し、与件文を読み、骨子を作り、回答を書き上げる必要があります。
この記事では、私が実践していた 「時間配分パターン」 と、その中で特に効果を感じていた工夫を紹介します。
実際、このやり方で解いた令和6年本試験での80分での再現回答はこちら↓
事例Ⅰの再現答案
事例Ⅱの再現答案
↓事例Ⅲの再現回答
まとめ
80分の時間配分は人によって最適解が異なりますが、「自分の型」を持つことで本番でも安定して回答を書き上げることができます。私の場合は、
■40分経過で必ず記述開始(記述開始時刻もメモ)
■与件文冒頭&末尾先読み
■解答手順を固定化
という3つの工夫で、時間切れ防止や効率的な回答をしていました。
全体の時間配分イメージ
私の場合の80分間の使い方の内訳はだいたい以下のように実施していました。
| フェーズ | 時間目安 | 主な作業 |
|---|---|---|
| ① 与件文冒頭&末尾を読む | 1分 | 企業概要・方向性の把握 |
| ② 設問解釈&メモ | 4分 | 設問要求の明確化、キーワード抽出、与件で拾うポイント整理 |
| ③ 与件文全体読み | 15分 | 設問と照合しながらマーキング(鉛筆一本スタイルなので下線や〇×やS、W、O、Tの記号) |
| ④ 骨子作成 | 20分 | 回答構成・要素整理 |
| ⑤ 記述(回答作成) | 40分 | 骨子に沿って文章化、骨子の未完成部分の仕上げ |
過去問練習で40分で記述を開始すればたいていの場合は問題を全部解くのには間に合いました。1問完成度を上げるよりも、全体を解いてなるべく得点が稼げるようにしていました。
私の場合はどういうキーワードを書くかや、言い回しを考えるのに非常に時間がかかってしまうので、なるべく骨子作成に時間が使えるような時間配分としていました。
設問解釈に時間をかけても与件文を読み始めるとそこまで頭に残ってないので、あまり時間はかけないようにしていました。
配点チェックはしていません。結局全部回答することが大事なのと、問題によって緩急をつけるという器用なことはできないからです。
工夫① 40分経過で骨子が途中でも記述開始
私は40分経過時点で骨子が完成していなくても、答案用紙への記入を始めます。
理由はシンプルで、なるべく早く回答用紙を埋めていくことで「80分の中で書き上げれそう」という安心感が得られるからです。
さらに、時間を絶対に間違えないために、記述を開始する時刻も問題用紙にメモします。
メリット
■書き切れないリスクを回避できる
■精神的な焦りを軽減できる
■ある程度エイヤで回答ができ、骨子作成で考えすぎる時間ロスを減らす
■早く終わったものから微修正ができる
この方法は、私のように骨子作成に時間がかかってしまう人には特におすすめです。
1問の時間をたくさんかけて完成度を高めた骨子を書いても、最終的に全ての問題を回答用紙に書き写せなければ落ちるリスクが高まります。
合格するために全体で6割を取ることを意識して、ある程度割り切ってでも、まずは全問書き上げることが大事です。
工夫② 与件文の「はじめ」と「最後」を最初に読む
与件文の冒頭と末尾には、企業の概要や現状、そして向かいたい方向性が書かれていることが多いです。
私は必ず最初にこの2段落を読みます。
メリット
■企業の全体像を早い段階でつかめる
■設問解釈の際にイメージがつかめたり回答の方向性が定めやすくなる
■与件文全体を読むときの「押さえておくポイント」がつかみやすい
工夫③ 回答手順の順番固定
私の回答手順は以下の通りです。
- 与件文の冒頭と末尾を読む
- 設問解釈(要求内容・制約条件を明確化)
- 設問ごとにメモ記入(キーワード・方向性)
- 与件文全体を読む(マーキングしながら(鉛筆一本スタイルなので下線や〇×、S、W、O、Tの記号))
- 骨子作成(解答構成)
- 記述(答案作成)
メリット
■与件文から「押さえるポイント」を最初に知れる
■設問と与件文の結びつけがしやすい
■80分の中で安定して記述を書き上げることができる
さいごに
試験本番の限られた80分を自分の型でやりきるために、過去問の練習から自分に最適な工程を考え、時間を意識して取り組むことが大事です。
自分の型が身につけば、本番でもいつもの練習と同じように回答書き上げることができ、試験全体で合格点に届くことにつながると思います。
これから受験される方は、2次試験の合格に向けて最後まで頑張ってください。

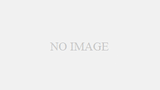
コメント